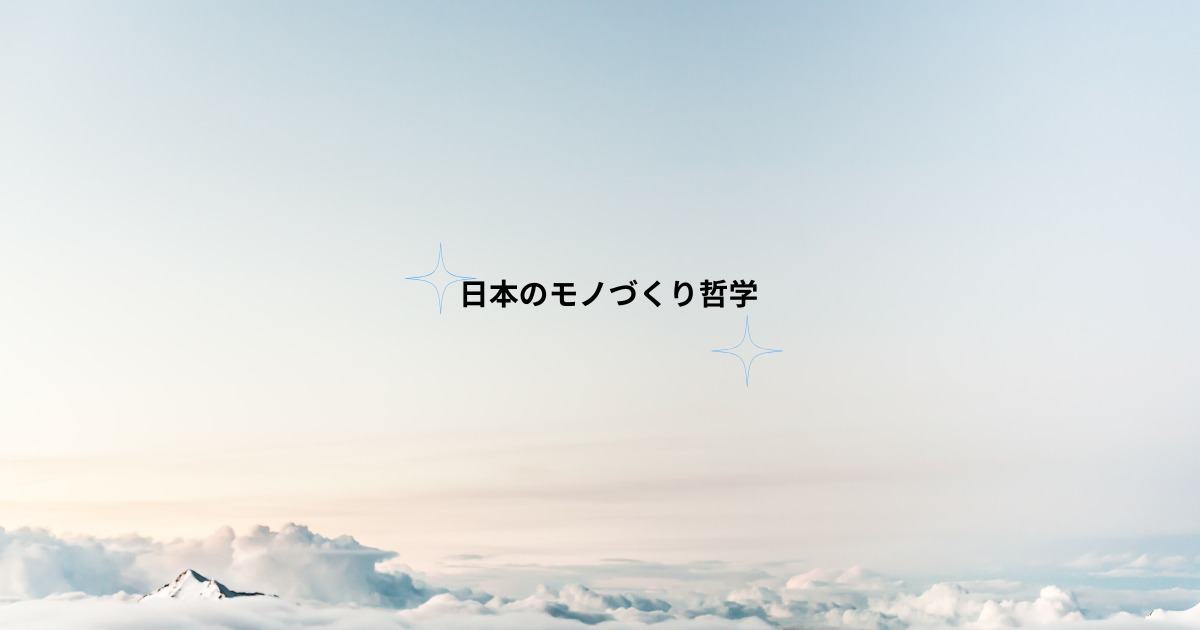企業の開発・生産組織能力の進化と製品開発力一般読者向けまとめたもの、著者は藤本隆宏、東京大学経済学部卒、三菱総合研究所・ハーバード大学博士課程を経て早稲田大学大学院教授、専門は技術・生産管理・進化経済学、
概要
迷走した日本のものづくり論、1)90年代の日本製造業論議―過剰反応、1990の自信過剰・2000の自信喪失、彼を知り己を知る、下からの戦略論、2既存の産業分類を一旦忘れよ、3アーキテクチャ(設計思想)のメガネで見る、戦略論、システム・コンポーネント・ステレオ、4アーキテクチャと組織能力の相性、統合型ものづくりシステム、モジュラー型のアメリカ、強い工場・強い本社への道、1日産復活の意味、ルノーと日産、開発のクロスファンクション制を本社に導入・ゴーン体制、ルノー・日産提携の意味、2ものくり企業の実力をどう測るか、企業実力を階層的に測る、ものづくりの組織能力、裏の競争力、表の競争力、収益力、3自動車に見るパフォーマンスの実態、4ITバブルの教訓、5強い工場・弱い本社症候群、6強い現場と強い本社を両立させよ、ものづくりの組織能力―トヨタ、1トヨタ的なものづくりから深く学ぶ、広く・深く学ぶ、トヨタ的なものづくり、2競争力と収益力、三層の組織能力、生産現場の統合能力、改善能力、製品開発管理の組織能力、購買管理、進化能力、カギは事後的対応力、進化能力を構成する要素、官僚制、心構え、組織能力の再評価を、体育会系の戦略論、相性のいいアーキテクチャで勝負しろ、1アーキテクチャとは何か、製品=基本設計とアーキテクチャ、2基本タイプはインテグラル・モジュラー・オープン・クローズド、モジュラー型とインテグラル型、クローズド型とオープン型、測定する、3アーキテクチャの産業論―事例、IBMとコンピュータ、オートバイと自転車、半導体、ソフトウェア、繊維・アパレル、鉄、お酒、アーキテクチャの産業地政学、1組織能力は歴史がつくるー日米、擦り合わせ型は日本、アメリカはオープン・モジュラー型、青木理論とアーキテクチャ戦略、2アーキテクチャの比較優位論、組織能力の偏在「得意技」、表現力のヨーロッパ企業はデザインブランド勝負の擦り合わせ、集中力の韓国は資本集中的なモジュラー製品、動員力の中国は労働集約的なモジュラー製品、ASEANは低価格の擦り合わせ製品で対中棲み分け、台湾はモジュラー戦略から擦り合わせ戦略、擦り合わせの日本グローバル戦略、中国との戦略的つきあい方、1中国ものづくりの多様性、製造現場、人件費、2中国的な勝ちパターンーアーキテクチャの換骨奪胎、地場産業乱立とシェア低下、疑似オープン・アーキテクチャ、中国家電のモジュラー的製品、ギャランツの戦略、弱点ー技術的ロックイン、3乗用車のアーキテクチャも換骨奪胎されるか、日本は戦略とオペレーションンの一致が必要、4中国で成功するアーキテクチャ戦略とは、疑似オープン・アーキテクチャにはコンポーネントビジネスで、擦り合わせと疑似オープンの両面戦略ホンダの動き、アーキテクチャシナリオに応じた中国戦略を、ものづくりの力を利益に結びつけよ、1アーキテクチャの両面戦略、ものづくり能力に見合った利益、得意な製品、苦手な製品、2アメリカ自動車メーカーのトラック戦略、巧みだったビックスリーの両面戦略、強い工場も必要、3アーキテクチャの位置取り戦略、なぜ位置取り戦略か、なぜアーキテクチャの位置取り戦略か、自社と顧客のアーキテクチャ、中インテグラル・外インテグラル、中インテグラル・外モジュラー、中モジュラー・外インテグラル、中モジュラー・外モジュラー、ポートフォリオ戦略、強い工場・強い本社への道、ものづくり日本の進路、1ここまでのまとめ―戦略再考、2さらなる能力構築に向けて―組織づくり、3日本のエクセレント・カンパニーに学べ、4トヨタの危機意識に学ぶ、5期間工の多能工化は可能か、6ITと「統合型ものづくり」のマッチング、7深いところからのブランド構築、8先行開発―日本のデスパー、9アーキテクチャの比較優位再論、10プロデューサーいでよ、11フロントランナー方式の産業政策、12文理融合のものづくり教育、社内教育、大学教育、シニア教育、13擦り合わせ大国日本の道、企業・官僚・コンサルタントにとって必読の書、
感想
相性のよいアーキテクチャで勝負せよと迫る、アーキテクチャの産業地政学を解説、
まとめ
迷走した日本のモノづくり論、強い工場・強い本社への道、ものづくりの組織能力、相性のよいアーキテクチャで勝負せよ、アーキテクチャの産業地政学、中国との戦略的つきあいから、ものづくりの力を利益に結びつけよ、ものづくり日本の進路を考察、