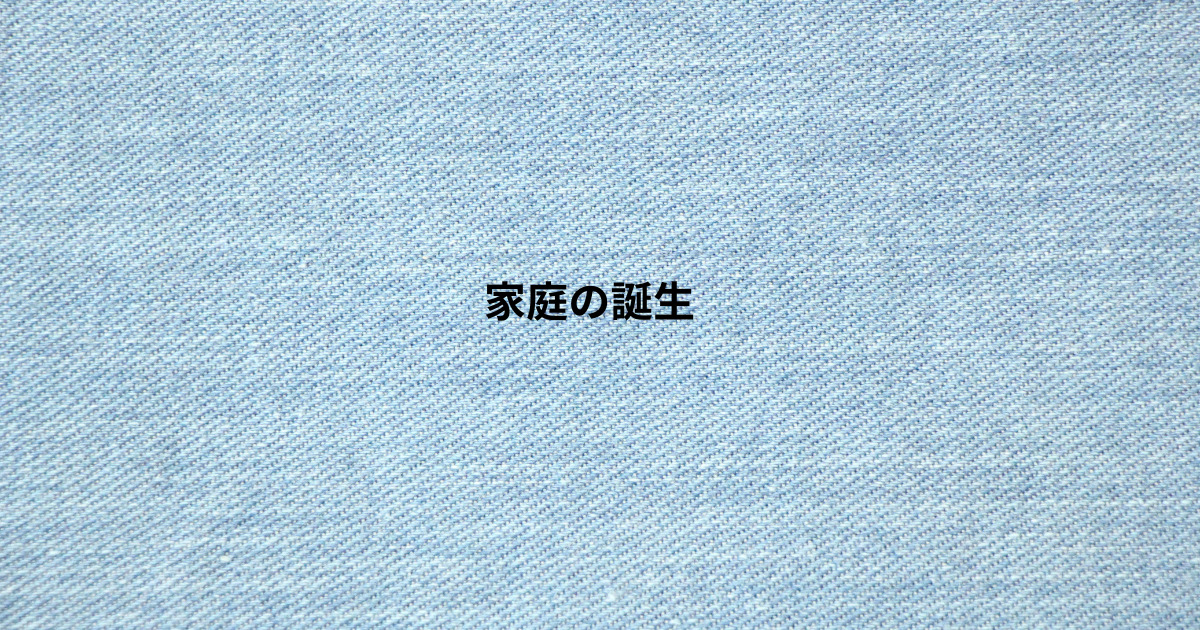本書は家庭について語ることと・社会構想を語ることは連動している立場から様々な対立を考察したものである、著者は本多真隆、慶應義塾大学大学院社会学研究科後期博士課程修了、現在は立教大学社会学部准教授、専門は家族社会学・歴史社会学、
イデオロギーとしての家庭
1家庭をめぐる錯綜、家庭という言葉、こども家庭庁をめぐって、家庭は日本の伝統的家族観ではなかった、保守系論者に敬遠された家庭、支配の場としての家庭、抵抗の場としての家庭、家庭の歴史をたどる意味、2本書の視点と方法、先行研究と本書の立場、分析の視点、用語の整理、
家庭の誕生ー「ホーム」の啓蒙
1家庭と文明化、家庭の建設、家庭の由来、福沢諭吉の家族論、キリスト教者とホーム、平民主義と家庭、2家庭の何が新しかったのか、家庭と近代家族、HOMEの不在、女坂に見る妻と妾、文明としての家庭、文明としての女性役割、天皇家の家庭化、庶民の家族生活、横の協同関係、庶民の結婚と性、3家庭と国家、家制度の形成、イデオロギーとしての家制度、家庭とナショナリズム、家庭を嫌った保守、家制度に組み込まれる家庭、良妻賢母と家庭、家庭小説の流行、社会主義と家庭、4理念先行の家庭、明治期の家庭とは何だったのか、理念と実態、ホームと家庭、
サラリーマンと主婦ー家庭と国家統制
1家庭と新中間層、家庭病の時代、サラリーマンの誕生、性別役割分業と教育する家庭、女中と家事、恋愛結婚という名のお見合い結婚、茶の間のある家、子ども本位の家庭改良論、2家庭と女性、新しい女の出現、個人であることと家庭、母性保護論争、3家庭と国家統制、保守系論調の動向、家族モデルのゆらぎ、家制度強化の頓挫、家制度と家庭の混合状態、保守系論調の迷走、家庭の展覧会、母の講座と家庭教育、4家庭と戦争、家の復古、私生活の否定、家庭の統制、母と戦争、兵士と家庭、
明るい民主的な家庭の困難ー家から家庭へ
1家制度の解体と存続、「青い山脈」の時代、明るい家庭の理想と困難、家から家庭へ、浮かび上がる家庭、家庭としての戸籍、生活基盤としての家の継続、相互扶助の家族精神は残さなければならない、2民主主義と「明るい家庭」は両立するか、肉体と個人、純潔教育と健全な男女交際、家庭科と民主主義、必ずしも明るく和やかにならない民主的家庭、マルクス主義と家庭、民主化論の陥穽とアクチュアリティ、3逆コースと家庭、家制度復活の兆し、孝養の義務化、均分相続と保守政権、反対運動の高揚と家庭への移行、べアテ・シロタ・ゴートンの苦闘、家庭の保護の二重性、4家庭の合理化、民主化と合理化、生活改善普及事業と家庭の民主化、新生活運動と明るい家庭、家庭と排除、
企業・団地・マイホームー一億総中流と家庭
1高度経済成長と家庭、新家庭論、民族大移動と核家族世帯の増加、企業社会の家庭、家電と団地、ライフイベントの施設化、商業化、高かった女子労働率、2マイホームの家族問題、家からホームドラマへ、男性の女性化とマイホーム主義、父親中心から母親中心の家庭へ、3家庭の再編と政治、保守政治の変容、人づくりから家庭づくりへ、家庭支援の構想、期待される人間像と家庭、4民主主義の模索と家庭、革新系の家庭論の困難、市民社会の基盤としての家庭、団地と民主主義、幼児教室の実践、仕事も家庭も・そして平等も、5一億総中流の実態、三世帯同居とホームドラマ、広域化する家族、自営商店と一億総中流、間接的な家庭支援と家庭の多様性、
理念と実態の乖離ーむき出しになる家庭
1家庭の飽和、個人化の時代、辛口ホームドラマの時代、金属バット殺人事件と家庭内暴力、2伝統化する家庭、家庭基盤の充実と伝統、日本型福祉社会という選択、A氏の人生と「家庭長」としての妻への依存、3家庭の限界、パート労働と単身赴任、キャリアウーマンと家庭、余裕を失う家庭、依存から自立へ、4バックラッシュと家庭、個人主義の否定、近代家族の代弁者としての保守系論者、高度経済成長期の保守、家庭教育の強調、家庭への介入、5孤立化する家庭、三世代同居の趨勢、雇用環境と未婚化、孤立化する育児、イデオロギーのひとり歩き、
家庭を超えて
家庭論の熱さ、近現代日本の家庭とは何だったのか、家庭と社会構造、個人と家族、個人化とエンパワメント、個人の保障と家族の再生、プライベートとインディビデュアル(個人)、個人と共同性、何を大切にしたいのか、家庭を超えて、
まとめ
イデオロギーとしての家庭、家庭の誕生、サラリーマンと主婦、明るい民主的な家庭の困難、企業・団地・マイホーム、理念と実態の乖離、家庭を超えて構成、本書は家庭の歴史をたどり・近現代日本の家庭を再考するものである、