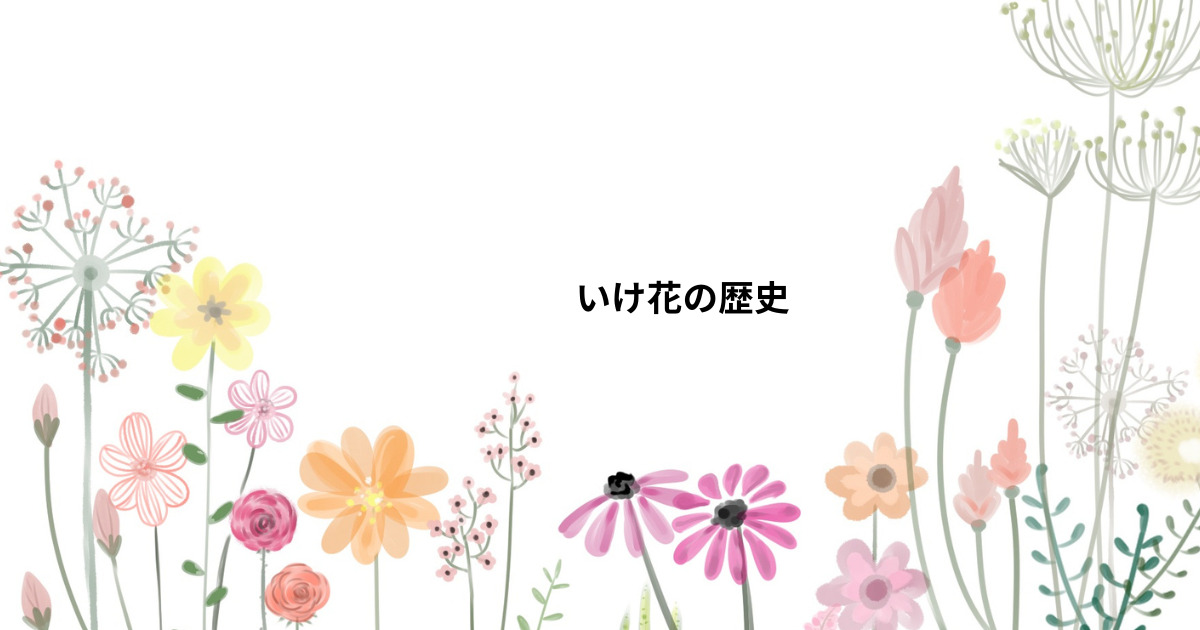二つの博士論文「花の成立と展開」と「帝国支配といけ花」で構成、著者は小林善帆、立命館大学博士号取得・名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程学位取得、現在は立命館大学衣笠総合研究機構客員研究員、国際いけ花学会参与、著書「花の成立と展開」他、
概要
いけ花を総称とする理由、たて花と立花、立花といけばな、生花、流儀形成、盛花成立、いけ花の源流、照葉樹林文化、依代、物合の花、鑑賞・行事の花、仏前供花と三具足の花、唐物趣味、様式の萌芽、七夕花合、15世紀の僧侶と花、淋汗の催し、物花の伝書の登場、同朋衆の花、山科言国とたて花、大沢久森のたて花、連歌会の花、花のネットワーク、花の伝書の登場、「仙伝抄」「文阿弥花伝書」「花王以来の花伝書」「華厳秘伝之大事」奥義の主張・和歌・座敷飾、「専応口伝」花の伝書に見られる稽古・心得、たて花の展開、天皇家・門跡・公家の愛好、武家の修得、立花様式、後水尾天皇と二代専好、鳳林承章と立花、花道、礼儀作法といけ花、男児の躾・嗜み、町人に広がり、いけ花から生花様式、源氏流、千家新流松月堂古流、無双真古流、町人の挿花会、中国花瓶の影響と文人生見立ての花・滑稽の花、生花様式の成立、遊芸、独習書、女性の嗜み、風流挿花会、遊女、武家女性、町娘、庶民女性、女大学、学制と遊芸、女学校、キリスト教主義女学校、明治維新と西欧の影響、博覧会、クララの日記、イサベラ・バード、外国人の眼差し、盛花の広がり、小原雲心・光雲・辻井引州・安達潮花・岡田広山・勅使川原蒼風、西川一草亭・山根翆堂・重森三玲、銀閣慈照寺、婦人雑誌とラジオ講座、ヘリゲリ夫人、川端康成、外地といけ花、台湾、朝鮮、樺太、満州、サイパン、青島、国際化の始まり、沖縄、前衛いけ花から造形いけ花へ、有吉佐和子「女弟子」、ラジオからテレビ、高度成長期以降、レジャー化、戦後台湾、戦後韓国、男性のいけ花、現代の銀閣慈照寺、教育基本法、インターネット、漫画、いけ花の歴史を綴る、
感想
花の伝書の登場と女性の嗜み,外地のいけ花まで網羅した通史、
まとめ
いけ花を総称とする理由、いけ花の源流、様式の萌芽、花の伝書の登場、たて花の展開、立花様式、「いけばな」から生花様式へ、女性の嗜み、明治維新と西欧の影響、盛花の広がり、外地といけ花、国際化の始まり、高度経済成長以降の考察、いけ花の源流から高度経済成長以降のいけ花の通史、