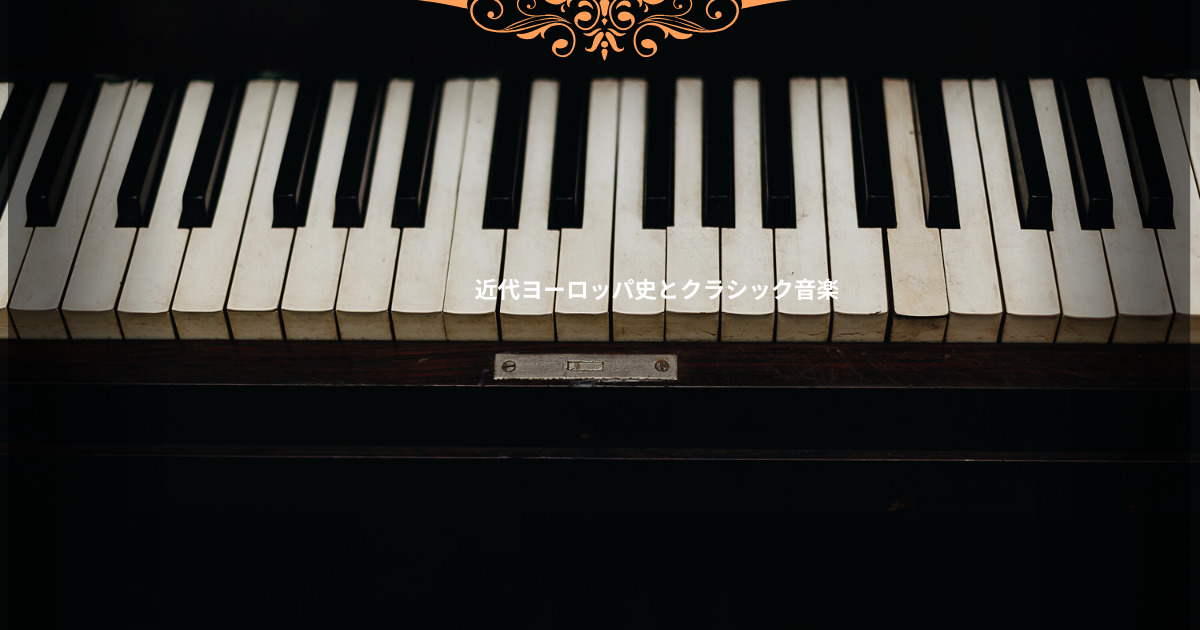クラシック音楽・個々の作曲家がどのような社会の中で作品を発信したか、作品がどのような社会的背景を持っているかを描写、範囲は啓蒙主義思想から両大戦までとする、著者は広瀬大介、音楽学者・評論家、青山学院大学教授、日本リヒャルト・シュトラウス協会常務理事、著書「楽譜でわかるクラシック音楽の歴史」
概要
啓蒙主義主義時代、貴族社会から市民社会、啓蒙主義・モーツアルト「魔笛」、ストーリーの謎、啓蒙主義、その頃日本、現代社会の基礎となった啓蒙主義、近代国家へイギリス、フランスは宮廷音楽この作品で体験、音楽史に影響を与えた啓蒙専制君主、1プロイセンのフリードリッヒ大王、2オーストリアのヨーゼフ2世、啓蒙主義時代最大の問題作―モーツアルト「フィガロの結婚」、ハプスブルグ帝国の検閲制度-文化政策、変わりゆくヨーロッパ社会、言葉を伴う歌曲やオペラ、ナポレオンの栄枯盛衰に見るベートーヴェンの理想と現実、交響曲第9に込められた変わりゆく社会へのメッセージ、庶民オペラとは流れを別にした風変わりな新曲ー第9の誕生、帝室と関わりを持たぬ時代の作曲家ー1820年代シューベルト、フランス音楽の新たな局面、ブルボン王朝の残照とロッシーニの傑作オペラ、ベルリオーズが最も輝いだ7月王政のブルジョワ文化、ポーランドはロシアの属国、フエデリック・ショパン、1独立を奪われたポーランド、2祖国ポーランドに寄せる想い・バラード、3ジョルジュサンドとショパンの愛、4愛の終わり、人生の終わり、近代的国家へと向かうドイツ、ザクセン王国が音楽的に充実した時代、ユダヤ教とキリスト教の狭間でーフェリックス・メンデルスゾーン=バルトルデイ、フランツ・リスト・またはリスト・フェレンツ、1国際人としてヨーロッパに生きる、2ヨーロッパの行く末を 変えた2月革命、3オーストリア=ハンガリー二重帝国の成立とハンガリーの音楽教育、ロベルト・シューマン、1ピアノ曲で紡いだ若き日の想いで、2)2月革命とその後、ヴェルディとワーグナージョゼぺ・ヴェルディ、1イタリア独立運動の始まり、2イタリア王国の誕生、リヒャルト・ワーグナー、1ドレスデン宮廷楽長から政治犯へ、2作曲家の保護者ルートヴィッヒ2世、バイトロイド祝祭劇場と「ニーベルングの指輪」、オペレッタを育んだパリとウイーン、オペレッタを育んだ二大都市・パリとウイーン、1フランス第二帝政とオッフェンバック、2「地獄のオルフェ」の大成功、東の帝都ウイーン―オッフェンバックとヨハンシュトラウス2世の出会い、ヨハンシュトラウス2世の「こうもり」と落日のウイーン、東ヨーロッパの胎動、ロシア音楽の夜明け、1ロマノフ王朝と近代ロシア音楽の祖・グリンカ、2ロシアの二つの音楽院とチャイコフスキーのピアノ協奏曲、チェコ王国の盛衰と19世紀の音楽、1ベトジフ・スメタナ、2アントニン・ドボルザーク、普仏戦争以降のフランスとドイツ、普仏戦争の終結とドイツ帝国の成立、普仏戦争以降のフランスとドイツ、1初の国民国家誕生に沸くドイツ、2サ二つのン=サンサーンス・フランクと国民音楽協会、ヨハネス・ブラームス、1作曲家が愛した故郷ハンブルグ、2交響曲への苦闘と新天地ウイーン、3晩年の内省的なピアノ小品集、クロード・ドビュッシー、1フランス第三共和国の時代、20世紀ピアノ音楽の祖、二つの世界大戦と作曲家、モーリス・ラヴェル、1フランス近代音楽を切り拓いた立役者、2大局的な視点をもった音楽家、セルゲイ・ラフマニノフ、1「交響曲第一番」の挫折を乗り越えて、2世相と作曲家の内面をえぐりだす傑作、ドミトリ・ショスタコーヴィチ「バビ・ヤール」、ベンジャミン・ブリテンとリヒャルト・シュトラウスの紀元2600年奉祝曲、レナード・バーンスタイン「キャンディード、
感想
個々の音楽家に注目する形で、作品の発信・作られた作品がどのような社会的背景を持っているかを考察、
まとめ
啓蒙主義時代、変りゆくヨーロッパ社会、フランスの音楽の新たな局面、近代国民国家に向かうドイツ、ヴェルディとワーグナー、オペレッタを育んだパリとウイーン、東ヨーロッパの胎動、普仏戦争以降のフランスとドイツ、二つの世界大戦と作曲家を考察、啓蒙主義時代から両大戦・音楽を娯楽として愉しむ時代までを描写、