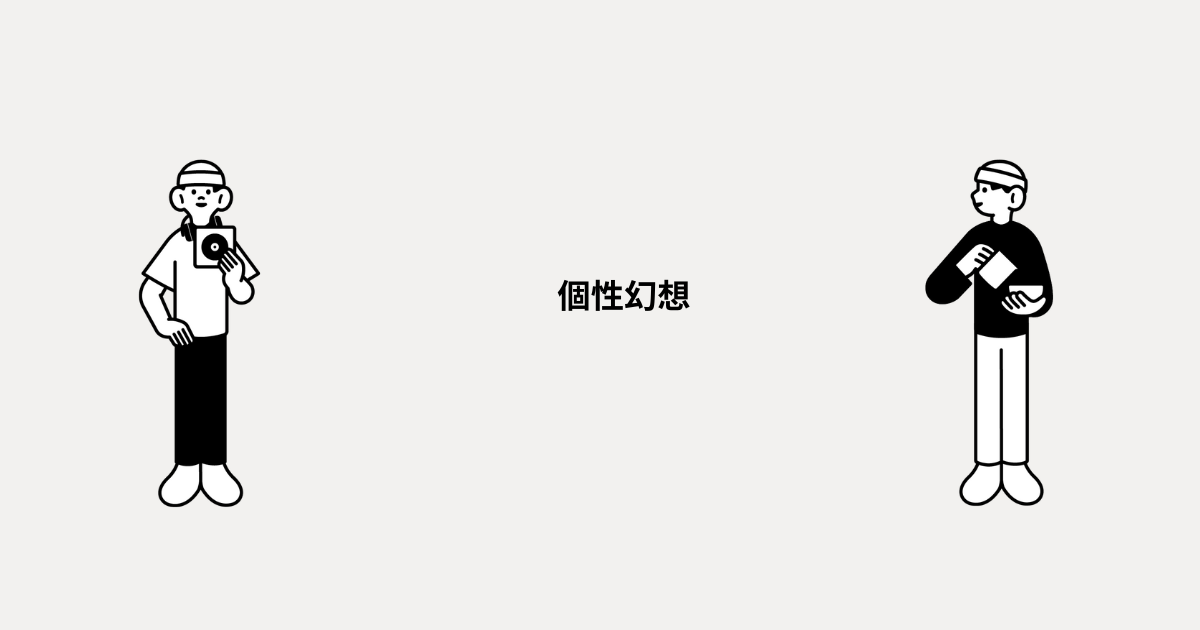盗癖も個性、鳥の目のアプローチ、分析視角・近代的疎外と個性で読み解く、著者は河野誠哉、東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学、東京女子大学現代教養学部教授、専門は教育社会学歴史社会学、著書「近代教育の社会理論」他、
概要
教育的価値としての浮上ー大正新教育と個性教育、1個性教育の時代、大正新教育と個性教育、一斉教授法誕生、集団的効率と個人的疎外、2成城小学校とドルトン・プラン,澤柳清太郎、成城小学校の創設、ドルトン・プランとは、挫折、個性教育とは何だったのか個人性を可視化する―個人調査の地平、1個性尊重訓令、教育政策への個性の取り組み、入学難問題、「個性調査」、2近代学校と表簿の実践、フーコーの試験論、表簿の個人化、カードという技法、3分析の対象としての個人、心理測定技術との結合、日本の心理学者たち、個性の把握、様々な個性、個性の生産、ブームの退潮、二度目のブームー臨教審と「個性重視の原則」、1トットちゃんのユートピア、窓際のトットちゃん、小林宗作と大正新教育、トモエ学園の授業スタイル、感性だけの新教育リバイバル、2閉塞する学校教育、学校荒廃、社会問題による現実の強化、学校不信の背景、学校教育の第二の完成期、3教育改革の時代、臨時教育審議会、原則としての教育の自由化論、個性の多義的用法による混乱、尊重と重視の間、個性化の誘惑-差異化のレトリック、1消費社会の中の個性、なんとなくクリスタル、ボードリヤールの消費社会論、強迫観念化する個性、2学校で個性はどう教えられてきたのか、学校カリキュラムとしての個性、道徳教育の沿革と学習指導要領、道徳カリキュラムの中の個性①中学校、道徳カリキュラムの中の個性②小学校、生徒の自己課題としての個性の伸長、どうやって伸ばすか、輝く個性、個性は教えられるか、実践からレトリックへー語彙論的考察、1個性の意味変容と二度のピーク、individuality からの乖離、データとしての図書タイトル、個性流通の二度のピーク、教育実践からレトリックへ、2派生語の展開―個性的・個性化・個性派、レトリックとしての個性、派生語①個性的、派生語②個性化、派生語③個性派、新教育の社会的帰結、障害と個性-包摂のレトリック、1障害も個性への共感と反発、五体不満足と個性、障害者白書の波紋、障害個性言説の論理的陥穽、共感の底堅さ、障害は個性のアンビバレント、個性はなぜ人々を苛ただせる、2個性の延長としての発達障害、発達障害、医療化のプロセス、空発達障害と個性の親和的関係、包摂と差異化の間、個性のゆくえ、近代化の反作用、価値としての自立、ポスト近代の個性、個性幻想を考察、
感想
個性主義も・蓋を開けてみれば閉塞状況へとつながる、
まとめ
教育的価値としての浮上、個人性を可視化する、二度目のブーム、個性化の誘惑、実践からレトリックへ、障害と個性、個性のゆくえを考察、個性の多義的用法により混乱をまねく、