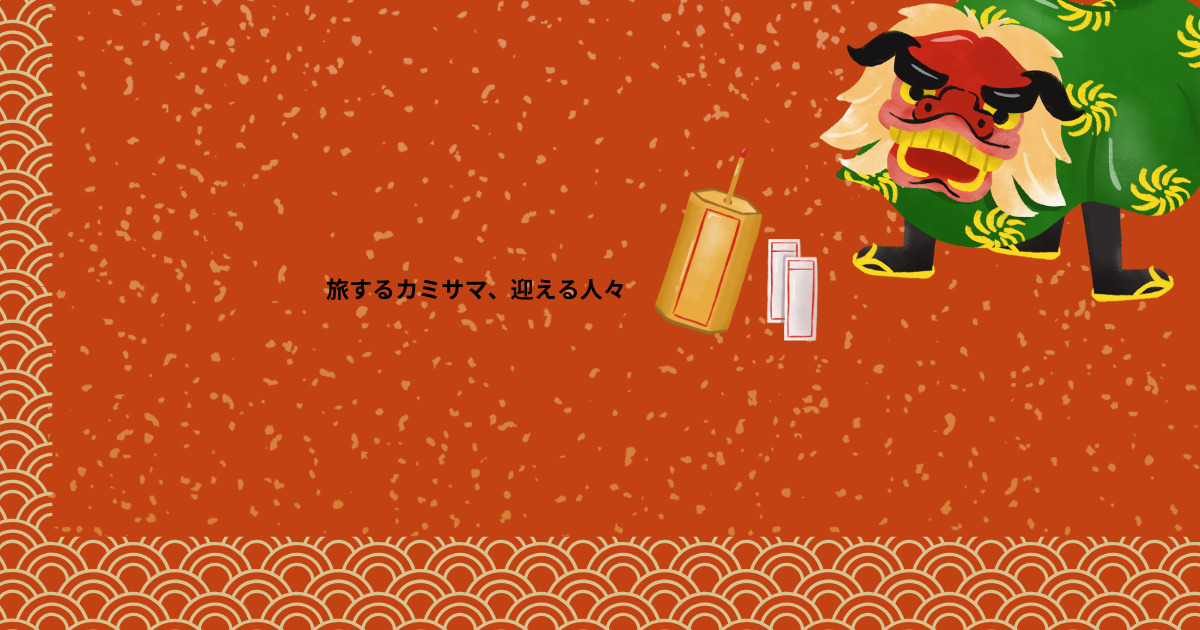著者は神野知恵、東京芸術大学大学院音楽研究科博士後期課程修了、岩手大学人文社会科学部人間文化課程准教授、専門は民族音楽学、民俗芸能研究、
家廻り芸能研究の提案、家廻り芸能との出会い、日常空間に芸能者がやってくる、穀物やお金をもらうことの意味、門付け研究から家廻り芸能研究へ、専業芸能集団の比較研究ー男寺研究と伊勢太神楽、ふたつの「まわす」、芸能の条件、分類、なぜ「家廻り芸能」か、文化価値の再発見をめざす、
伊勢太神楽と現代日本を歩く、伊勢大神楽とは何なのか、家を廻る獅子舞の風景、日本と韓国の放浪芸への視点、道を行くプロの再発見、小豆島での初調査、近江の正月行事、風の人と土の人、符牒について、わしわはわしら、総舞を見なければわからない、オシシサンはカミサマそのもの、獅子頭の最終目的地、歩き旅に特化した楽器たち、笛の音が伝えてくれること、笛は芸能交流の媒体、年に一度のお伊勢参り、長持ち大解剖、地域の人々とのかかわり、もなかの教訓、四季の移ろいを渡り歩く、備前のシシと獅子の対決、瀬戸大橋のかかる島で、神さんの終活、島に咲く新しい風、コロナ過を通じて見えたこと、初期コロナ禍の混乱、神楽は精神安定剤、神楽と薬と流行り病、リモート厄払いはアリか、獅子舞とカメラを止めるな、、人々の記憶に残る伊勢大神楽、お金では買えないご縁・カグラヤド、檀那場の再開発、松井さんの想い出ばなし、朝鮮から来た神楽師の墓、真似事に心血をそそぐ加茂神楽、ニセモノとホンモノのあいだ、ひとつとせ・ひとつお伊勢の大神楽、先祖との邂逅、追悼・三木浩一さん・タミさん、国際交流と公演企画・現代的な伊勢大神楽の解釈、韓国公演に見る伊勢大神楽の現場性、お祓い廻りは海を越える、みんぱく村での社会実験、カグラの動くデータベース、フィールドノート・家を廻る芸能津々浦々、1黒森神楽、2答志島獅子舞、3八代妙見祭獅子舞楽、4小村井香取神社獅子巡行、5福野横丁獅子舞、6湖山茶屋麒麟獅子舞、7川内鹿踊、8じゃんがら念仏踊、9中堂寺六斎念仏、10吉浜のスネカ、権現様、ウタイコミ、11浦浜念仏剣舞と韓国農楽の国際交流、12阿波木偶まわし、旅するカミサマと迎える人々の執拗ともいえる調査研究、
感想
家廻り芸能研究は、伊勢大神楽があり、迎える人々とのつながりで成立していることを実感、
まとめ
家廻り芸能研究の提案、伊勢大神楽と現代日本を歩く(伊勢大神楽、地域の人々との関わり、コロナ過を通じて見えたこと、人々の記録に残る伊勢大神楽、国際交流と公演企画)、フィールドノート・家を廻る芸能津々浦々(黒森神楽、答志島獅子舞、八代妙見祭獅子舞楽、小村井香取神社獅子巡行、福野横町獅子舞、湖山茶屋麒麟獅子舞、川内鹿踊、じゃんがら念仏踊、中堂寺六斎念仏、吉浜のスネカ・権現様・ウタイコミ、浦浜念仏剣舞と韓国農楽に国際協力阿波木偶まわし)を考察、旅するカミサマと迎える人々との信仰・信頼関係を調査、