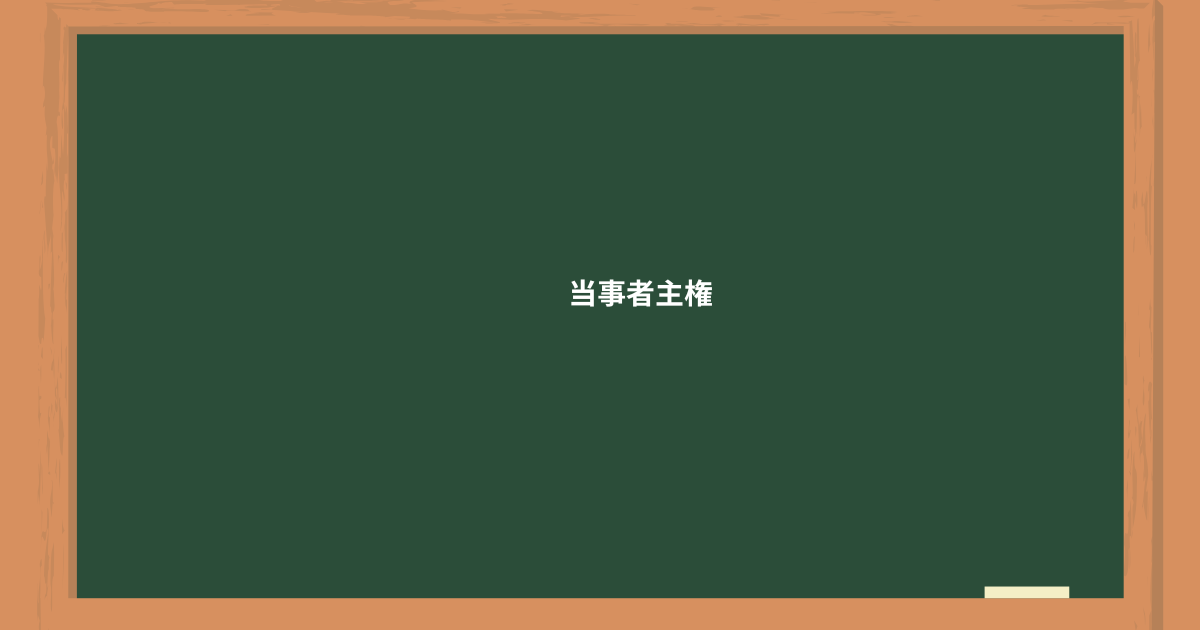当事者主権とは自己の身体と精神に対する誰からも侵されない自己決定権、ラディカルな民主主義を目指している、著者は中西正司、交通事故で四肢まひ、86年自立生活センター・ヒューマンケア協会設立、全国自立生活センター協議会顧問・ヒューマンケア協会代表、著書「自立生活運動史」、上野千鶴子、社会学者、東京大学名誉教授、著書「世帯間連帯」他、
概説
当事者宣言、1当事者主権とは何か、2当事者であること、3自立支援と自己決定、4当事者になる、5医学モデルから社会モデル、6当事者運動の合流、7専門家主義への対抗、8当事者学の発信、9公共性7の組み換え、当事者運動の達成してきたもの、1当事者運動の誕生、2自立生活運動の歴史、3自立とは何か、4自立生活センターの成立、5自立生活支援という事業、6当事者の自己決定権とコミュニケーション能力、7介護制度をどう変えてきたか、8自立生活運動の達成してきたもの、9新たな課題、介護保険と支援費制度、1介護保険が生まれてきた背景、2介護保険の老障統合をめぐって、3支援費制度のスタート、4介護保険と支援費制度の違い、5育児の社会化をめぐって、当事者ニーズ中心の社会サービス1属人から属性へー自分はそのまま変わらないでよい、2誰が利用量決めるか、3誰がサービスを供給するか、4社会参加のための介助サービスをどう認めるか、5家族ではなく当事者への支援を、当事者たちがつながるとき、1システムアドボカシー、2縦割りから横断的な連携へ、3ノウハウの伝達と運動体の統合、4組織と連携5適正規模とネットワーク型連携、6法人格の功罪、7事業体と運動体は分離しない、8採算部門は不採算部門に対して必ず優位に立つ、当事者は誰に支援を求めるか、1障害者起業支援、2介護保険と市民事業体の創業期支援、4規制緩和と品質管理、5雇用関係、6ヘルパーに資格は必要か、ダイレクト・ペイメント方式、7ケアワーカーの労働条件、当事者が地域を変える、1福祉の客体から主体へ・さらに主権者へ、2家族介護という常識、3施設主義からの解放、4精神障碍者の医療からの解放、5脱医療と介助者の役割、6医療領域の限定、7サービス利用者とサービス供給者は循環する、当事者の専門性と資格、1ヘルパーに資格は必要か、2ビアカウンセラーの専門性、3資格認定と品質管理ーフェミニストカウンセリングの場合、4ケアマネジャー化・ケアコンサルタントか、5ケアマネジャーの専門性と身分保障、6成年後見制度と全人格的マネジメントの危険性、7新しい専門性の定義に向けて、当事者学のススメ、1女性運動と女性学、2性的少数者とレズビアン・ゲイ・スターディーズ、3患者学の登場、4自助グループの経験、精神障害者の当事者研究、6不登校学のススメ、7障害学の展開、2003年以降の障害者運動と新たな法制度、1支援費制度の破綻と介護保険との統合問題、2障害者自立支援法の成立、3自立支援法のもたらしたもの、4相談支援とケアマネージ孟とャー、5政権交代・障害者権利条約障害者総合支援法、6総合福祉部会、7障害者差別k際商法、8Nothing about Us Without Us,全国に展開する自立生活運動、そして世界へ、1全国へ広がる自立生活センター・自立生活運動、2事業体と運動体のはざまで、3新しい障害の増加、4世界へ、5DPI世界会議と世界の障害者との連帯、介護保険以後の高齢者福祉、1当事者ではなかった高齢者、2介護保険成立の経緯、3財源と給付、4介護保険の制度設計、5意図した効果、6意図せざる効果、7サ高住という抜け穴、8脱施設化へ、介護4保険の達成と危機、1現場の進化、2危機に直面する介護保険、3コロナ過のもとの介護事業、4崖っぷちの介護保険、5乗り越えた三つの分断、6再家族化と市場化、7介護保険はどこに向かうか、MeToo以後の女性運動、1声をあげた性暴力被害者、2拡がる運動の裾野、3Me Too運動の効果、4定義が変わり法律を変える、5制度を変える当事者、6政治を変える、当事者研究の新展開、1当事者研究の登場、2当事者研究の拡がり、3多様化する当事者研究、当事者宣言、主権は当事者にあり、
感想
障害者自立生活センターを立ち上げた中西正司と女性学の上野千鶴子の感動の共著「当事者主権」、障害者、高齢者も変わる、自立のための行進を始めた、
まとめ
当事者宣言、当事者運動の達成してきたもの、介護保険と支援費制度、当事者ニーズ中心の社会サービス、当事者がつながるとき、当事者は誰に支援を求めるか、当事者が地域を変える、当事者の専門性と資格、当事者学のススメ、2003年以降の障害者運動と新たな法制度、介護保険以後の高齢者福祉、介護保険の達成と危機、Me Too以後の女性運動、当事者研究の新展開を考察、定義が変わる、法律を変える、制度を変える、政治を」